(株)日立ハイテクの鈴木康平さんへのインタビューから考える
―「主体的に学び、働く」理学教育が育む職業能力とは

「自分が何をしたいか、どうしたいかを自分の頭でちゃんと考えて、次に、そのためにはどうすればいいかを計画し、きちんと自分の仕事をすること。仲間とのチームワークは大事にしつつ、自分の芯はもって、流されることなく働くこと。それが自分にとってハッピーな働き方です。自分はそのベースを、茨城大学での6年間で得たのだと確信を持って言えます」。
2017年に理学部を、2019年に大学院理工学研究科博士前期課程を卒業?修了し、現在は株式会社日立ハイテクに勤める鈴木康平さんは、インタビューでそう力強く語った。その鈴木さんの横では、かつての指導教員である横山淳教授が「我が意を得たり」という表情を浮かべている。
時を戻そう。
2012年、日立第一高等学校の3年生だった鈴木さんは、『物理チャレンジ!』という中高生を対象としたコンテストに挑戦していた。「誰かやってみないか」という先生の呼びかけに対して立候補し、手作りの実験機器で音速を測るという実験に取り組んでいた。高校の勉強で一番好きなのが物理。素粒子のことに興味をもっているものの、本を読むだけでは大まかなことしかわからない。もっと論理的に、体系的に学んでみたい―地元の大学で物理を学ぶという道は自ずと拓けていた。
茨城大学理学部に入学後、同じ物理学コースの友人たち―もちろんみんな物理のファン―とはすぐに打ち解けることができた。鈴木さんが2年生のときに天下足球网の図書館がリニューアルされた。可動式のテーブルやホワイトボードが並ぶ「ラーニングコモンズ」もせっかくだから使ってみたいと思い、コースの友人たちと一緒に課題に取り組んだことをよく憶えている。
「1年生までは教養の科目が中心で、物理学コースらしい専門的な授業があまりなかったのですが、2年生になると演習の授業が始まり、ちょっとやそっとでは解けない、数式をこねくり回すような理論の問題がほぼ毎週出されるようになりました。それをみんなでやってましたね」。
ここで身に付いたことのひとつが「数式をいじる感覚」だと言うが、実はそれだけに留まらない。「実際に目の前の数式を解いてみると、ただ結果を出すだけでは満足できなくて、その結果にどんな意味があるのかもだんだん考えるようになってきたんです。物理学も結果を出しただけでは意味がなく、それを説明することが大事。その素養は演習で学んだと思います」。
こう振り返る鈴木さんの言葉を聞き、当時鈴木さんたちの学年の演習を担当していた横山淳教授は、「それは僕たちも意識していることです」と話す。「自分で考えて答えを出し、それがどういう意味、どんな発展性やつながりがあるのか、あるいは実社会にどう結びついているかまで考えられるような、そのトレーニングとなる問題を考えています」。
久々に訪れた実験室で横山教授と談笑する鈴木さん
理学部では3年生の終わりに所属する研究室を選択する。大学での学びを進めるうちに「物性」への興味が強まっていた。「素粒子や宇宙に比べると、物性は高校生にとっては魅力がわかりづらい分野ですよね。でも量子力学や熱力学、統計力学を勉強していくと、物や原子1個ではわからない世の中の現象が、それらがたくさん集まった状態を調べることで説明できるようになるということに、おもしろさを感じるようになってきたんです」と鈴木さん。その当時、横山教授担当の実験の授業で、ティーチングアシスタント(TA)を務めていた大学院生とやりとりしながら超伝導体の作製に主体的に取り組んだ経験も印象に残っている。「実験や研究を進める上でグループに馴染むことができるかは大事です。先輩たちの雰囲気に触れながら、このグループなら溶け込んでいけるかもしれないと感じることができました」。
卒業研究では、超伝導を示す化合物の磁場の様子や温度の変化を見ながら、超伝導の要因となる「量子揺らぎ」の動態をつかむという研究に取り組んだ。実験を繰り返しながら、化合物を自分で設計して超伝導の起こりやすさをコントロールできるぐらいにまでなってきた。
卒業後に大学院で進学するというイメージは早くから持っていたが、このまま茨城大学の横山研究室で研究を続けるか、あるいは他の大学の大学院に進学するか、「2つの選択肢があった」と鈴木さんは振り返る。そんな中、東京大学の実験施設を借りて試料の測定を行う「出張実験」に参加した。茨大で研究を続けるというキャリアイメージは、先輩たちの姿からリアルに想像できていたが、出張実験を通じて東大の研究者とも交流することで、他大での院生生活のイメージも湧き、両方の「選択肢」がより明確になった。「自分が2年間、その場に溶け込みながら主体的な研究に取り組むことができて、なおかつ他大学の人たちとの議論もできるのであれば、それが一番自分の成長につながるのではないか」という思いが強まり、茨大の大学院への進学を決めた。 横山教授によれば、鈴木さんがまさにそうだったように、「出張実験」の取り組みには、学生が主体的にキャリアを選ぶ上でのイメージを提供するという狙いがあるという。加えて、茨大であろうと東大であろうと、サイエンスの研究はどこにいても「先端」のものであるという感覚を、学生たちに持ってもらいたいという思いもあったという。「僕らは選択肢となる情報を示すけれど、選び取るのは学生本人。マスター(修士課程)の2年間をどう楽しく過ごすかは、その人の人生にとって大事ですよね。鈴木さんは自分のペースで自主的にやっていくということを最優先して、自分のキャリアを自分でちゃんと選び取ったということです」と横山教授は語る。
横山教授によれば、鈴木さんがまさにそうだったように、「出張実験」の取り組みには、学生が主体的にキャリアを選ぶ上でのイメージを提供するという狙いがあるという。加えて、茨大であろうと東大であろうと、サイエンスの研究はどこにいても「先端」のものであるという感覚を、学生たちに持ってもらいたいという思いもあったという。「僕らは選択肢となる情報を示すけれど、選び取るのは学生本人。マスター(修士課程)の2年間をどう楽しく過ごすかは、その人の人生にとって大事ですよね。鈴木さんは自分のペースで自主的にやっていくということを最優先して、自分のキャリアを自分でちゃんと選び取ったということです」と横山教授は語る。
トップレベルの研究ができているという充実感を感じさせ、「楽しい」研究生活につながる選択のための情報を示すという横山教授のスタンスは、大学院での研究指導でも発揮された。鈴木さんはマスターの2年目に、イギリスとアメリカを立て続けに訪れた。
「イギリスに行ったのは、オックスフォード近郊にある大型加速器施設を使った実験をするためです。(東海村の)J-PARCでも量子ビーム実験はできるかもしれませんが、横山先生から『せっかくだから行ってみようか』と声をかけていただき、1週間ほど滞在してミュオンを使った実験をさせてもらいました。」
「また、アメリカの方は、サンフランシスコで行われた物性の磁性に関する1000人規模の大きな国際会議。これも横山教授に「行ってみないか」と言われ、飛び込んだものだ。そこでは修士論文で取り組んでいた研究成果を発表。「日本の学会に比べて、すごくフレンドリーに話を聞いてもらえたと感じました。ひとつひとつのポイントについて丁寧にリアクションしてもらえましたし、若い研究者たちと同じようにフランクな感じで歩き回っているのが、実は世界的に著名な研究者だったりとか、とても印象的でしたね」。
その後鈴木さんの研究成果をまとめた投稿論文が、アメリカ物理学会の学会誌にアクセプトされた。自ら選び取った6年間の学生生活を、自身がメインとなる論文の掲載という最高の形で結実させることができた。
イギリスでの実験から帰ってきたタイミングと前後して就職活動に取り組み、5~6社ほどの面接を受けた。「大学で培った考え方を活かすことができ、最先端の技術に携われる仕事がしてみたい」と、現在勤める株式会社日立ハイテクに入社した。今は半導体の工場で使用される電子顕微鏡(測長SEM)の設計の仕事をしている。2月には台湾の顧客先で開発に携わった装置の納品に立ち会い、設計に従事する立場でありながら、顧客先の最前線で対応されている方々の声を直接聞くという貴重な機会を得た。
「設計の工程で詳細をしっかりと詰めることが、製品としての信頼性や価値を高めるだけでなく、製品をメンテナンスする方々の負担を軽くすることにもつながります。逆に、そこに足りない点があると最前線で対応される方々の負担が重くなるということ。それを改めて意識させられました」と鈴木さん。 そしてようやく冒頭で紹介した言葉が出てくる。
そしてようやく冒頭で紹介した言葉が出てくる。
「自分が何をしたいか、どうしたいかを自分の頭でちゃんと考えて、次に、そのためにはどうすればいいかを計画し、きちんと自分の仕事をすること。仲間とのチームワークは大事にしつつ、自分の芯はもって、流されることなく働くこと。それが自分にとってハッピーな働き方です。自分はそのベースを、茨城大学での6年間で得たのだと確信を持って言えます」。
サイエンスを追究する理学部での学びは、基礎研究としてのおもしろさはあっても、研究者にでもならない限りは、社会人としての職業能力の育成には直接はつながらないと思われがちだ。しかし、鈴木さんと横山教授の話を聞く限り、それは明らかな誤解だとわかる。いや、誤解どころではない。「結果を出しただけで満足せず、その結果の意味を主体的に考える」ということを学生に求め、そのトレーニングとしての教育を教員が強く意識しつつ、他方で「先端」の研究を行う対等な同志としても学生を捉えるという理学部の教育は、より本質的な意味で、主体的な職業人を体系的に育てているといえないだろうか。
「サイエンスをやることの自由さと、一方でそれにどうアプローチするかという客観性を担保するための理学教育です。少なくともうちの研究室では、僕が言っていることがすべて正しいとは限らないからね、だから自分の考えはどんどん話してほしいと、学生たちに伝え続けています」と横山教授。
その教育の成果は、鈴木さんたち卒業生の生きざまがまさに示してくれている。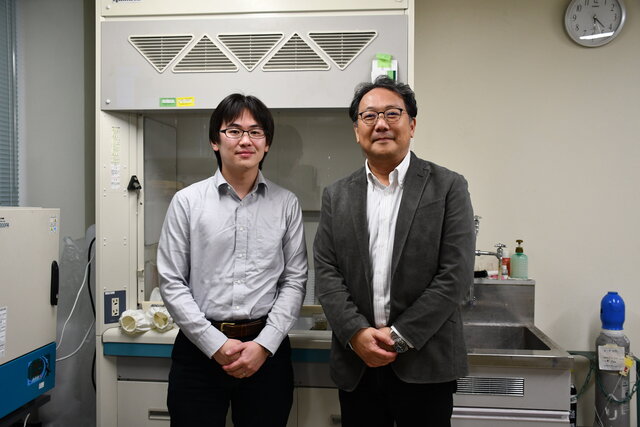
(取材?構成:茨城大学広報室/(株)日立ハイテクでの撮影写真は同社提供)




